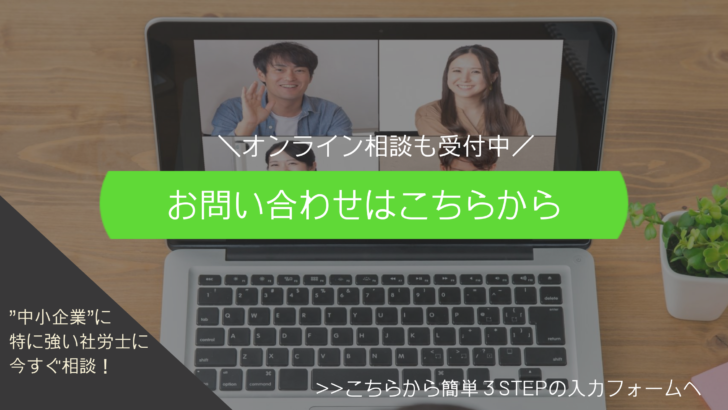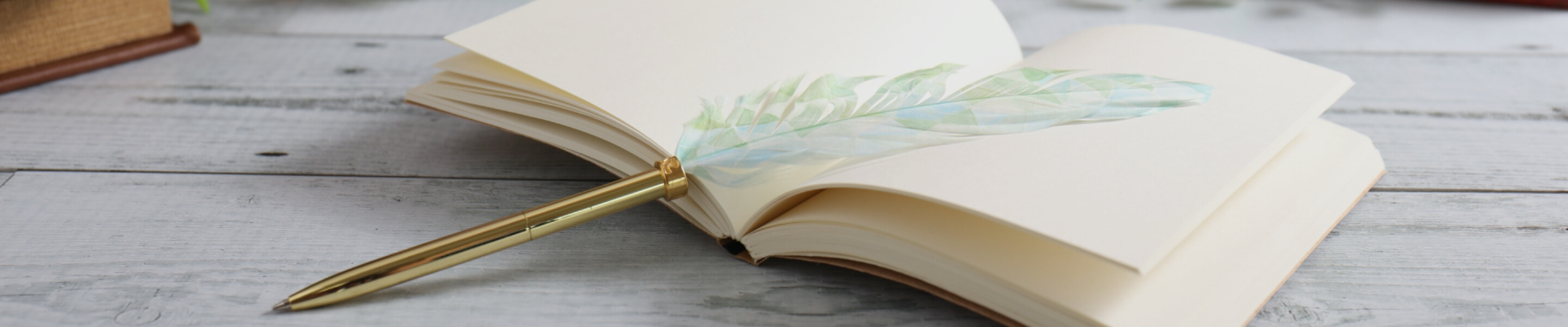

働き方改革とは、一億総活躍社会を目指すための働き方に関する改革のことで、すべての中小企業、大企業が関係する取り組みです。
労働人口が減少して残業時間が増えている日本では、国全体の生産性を上げることが必要です。
そのための取り組みが、働き方改革です。
本記事では、働き方改革の概要や目的、具体的な法律や押さえておくべきポイントを解説しますので、ぜひ今後の働き方を見直す際にお役立てください。
目次:タップで該当箇所へジャンプ
働き方改革とは

上述したように、働き方改革とは、一億総活躍社会を目指すための改革のことです。
また、一億総活躍社会とは「50年後も人口一億人を維持して、職場、家庭、地域問わず、誰もが活躍できる社会のこと」を示します。
首相官邸のWebサイトでも、働き方改革に関して下記のように記載がされています。
働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。(出典:一億総活躍社会の実現)
ここでは、働き方改革の目的やその背景に関してご説明します。
働き方改革の目的
働き方改革の目的は、生産性の向上です。
現状の日本は、個々人のスキルレベルによって生産性が大きく異なります。
生産性が異なること自体は悪くありませんが、一部の人だけが高い給与をもらっていたり、反対に給与が低くて生活がままならなかったりする人もいるかもしれません。
これらの格差をなくすためには、国全体としての生産性向上が必要であり、それが結果的に格差をなくすことにも繋がります。また、生産性が向上すれば仕事や家庭・地域などのコミュニティが活性化し、全体が生きやすい国へと変化させていくことも可能となります。
▼生産性向上の方法について、詳しくは下記の記事をご覧ください
【社労士監修】生産性向上とは?企業が行うべき取り組みや、役立てたいツールを徹底解説
なぜ今働き方改革か
働き方改革と謳われ始めた背景には、日本の労働人口の減少にあります。内閣府は日本の将来人口推計を発表しており、それが下記のとおりです。
- 2050年:9,000万人
- 2105年:4,500万人
本記事を執筆している2021年時点では、日本の人口は約1億3,000万人であり、約30年後には4,000万人の人口が減少することになります。
また「少子高齢化」と言われているように、働けない高齢者の方が増えることも同時に予想できるため、労働人口が少なくなり、日本の生産性はさらに下がってしまう恐れがあります。
これらのリスクを防ぐための動きが働き方改革です。
実際に働き方改革が成功すれば、人口は減少すれど、生産性自体が高まっていくことは間違いないでしょう。
働き方改革の3つの柱

ここからは、下記3つの働き方改革の柱をご説明します。
- 長時間労働の是正
- 正規・非正規社員の格差是正
- 柔軟な働き方の実現
それぞれ順番に見ていきましょう。
長時間労働の是正
まずは、長時間労働の是正です。
「過労死」といった言葉が生まれるほど日本の残業問題は顕著であり、心を病んでしまったり、体を壊してしまったりする人も多くいます。
また、本来の生産性の要である30代〜40代の残業が特に多いことも問題です。
働き盛りの年代の社員の生産性が落ちてしまうと、結果的にそれらの人から仕事を受ける20代の生産性も落ちてしまうため、長時間労働は早急に解決しなければならないと言えます。
正規・非正規社員の格差是正
次に、正規社員・非正規社員の格差を是正する必要もあります。
日本は、正社員経験がない人に対して批判的な視点を持ったり、転職の機会でスクリーニングしたりします。
しかし、正規社員になったことがないからと言って、その人の生産性が悪いことに繋がるわけではありません。
また、正規・非正規社員の格差の是正をしなければ、出産や育児等で非正規社員に望んでなりたい人が一歩を踏み出せなくなります。
柔軟な働き方の実現
最後は、柔軟な働き方の実現です。2020年に新型コロナウイルスが蔓延して以降、リモートワークやテレワークといった働き方が注目されるようになりました。
結果的に、同じ会社に働きながら地方に移住したり、出社したい時間に出社したりできる企業も増えたことも事実です。
こういった柔軟な働き方を企業も促進することで、社員満足度の高い企業を作り上げることができ、結果的に社員の生産性を向上することに繋がります。
働き方改革で改正された8つの法律

働き方改革では、下記8つの法律が改正されました。
- 時間外労働の上限規制(罰則あり)
- 勤務時間インターバル制度の導入
- 年5日以上の有給休暇取得義務
- 月60時間以上の時間外労働に割増賃金率の引き上げ
- 同一労働・同一賃金の原則
- フレックスタイム制の柔軟性拡大
- 高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働)の創設
- 産業医・産業保健機能と長時間労働者に対する面接指導等時間の強化
特に、時間外労働の上限規制には注意する必要があります。
業種業態によっては、どうしても残業をしなければ業務が回らない場合もあるかもしれませんが、新たな罰則も制定されているため、必ず内容を確認しておきましょう。
働き方改革で押さえておくべきポイント

働き方改革では、下記3つのポイントを押さえておくことが重要です。
- 労務管理システムの導入
- 助成金制度の活用
- ガイドラインの確認
それぞれ順番に見ていきましょう。
労務管理システムの導入
労務管理システムとは、社員の労務管理の手続きを効率化できるシステムのことです。
月間の出勤日数や労働時間をひと目で把握できるため、残業が多い社員の仕事量を減らしたり、少ない社員に新たな仕事を依頼したりするなど、労務管理をする際のコストを削減できます。
助成金制度の活用
次に、助成金制度も積極的に活用しましょう。
中小企業の多くは、新たなことに投資するためのキャッシュフローが潤沢ではないせいで、社員に還元できる給与やシステムの開発にお金をかけることができない場合があります。
そこで役立つのが助成金制度です。
たとえば、キャリアアップ助成金や業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金などの助成金制度が挙げられます。
これらの制度をうまく活用することで会社のキャッシュフローを安定させることができ、社員に給与で還元したり新しいシステムを導入できたりすることに繋がります。
都道府県労働局や地方自治体に助成金制度利用の相談窓口がありますので、まずは気軽に相談してみることが大切です。
ガイドラインの確認
最後に、働き方改革に関するガイドラインを確認しておきましょう。
働き方改革の概要を知っていたとしても、細かなルールに関する知見がないばかりに、知らない間にガイドラインを違反していたといった事態が起きかねません。
まとめ
働き方改革の概要や背景、それらを実行するためのポイントを解説してきました。
これからの日本は、労働人口の減少、高齢化の進行により、このままの状態を放置していると労働生産性が低下してしまいます。
これらを防ぎ、一億人全員が活躍できる社会を目指すためには、働き方改革のガイドラインを熟知し、働き方改革を一つ一つ実行していくことが必要です。
まずは、働き方改革のガイドラインを確認した上、助成金制度を活用し、社員の生産性が上がる工夫をすることから始めてみてはいかがでしょうか。
働き方改革へ対応に向けて、勤怠管理システムの導入、助成金制度の活用、労働環境の改善などでお悩みの方はぜひ、フェニックスマネジメントへご相談ください。